interview
聞きたい
【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶︎42】
高校2年冬-3
2023.04.15

新調したグローブ いまも
年末が近づくにつれて周囲からの擦りこみ効果や現実的な可能性から、実質的な甲子園出場内定モードになっていった。
川北はグローブを新調することにした。関東大会は一部補修して乗り切ったものの翌年の夏までもつとは思えなかったし、何といっても甲子園である。恐る恐る親に切り出すと即答で「買いなさい」であった。
ミズノ社、ワールドウィンの3塁手用グラブが発売されていた。見た瞬間にもう決めていた。これまでの内野手用と比べるとやや深く、網の部分の下の方が革張りで補強されている。いかにも右打者の痛烈な打球の多い3塁手用だと感じた。
大事に保革油をつけ、ボールを入れて型作りをした。それから40年以上、いまだに手元にある。
ピカピカに保たれているとはいえない。さすがに内皮もボロボロにはなっているがグローブとして立派に機能する。時折、手にはめている。外すと左手に何ともいえない匂いが付く。ずっと変わらない匂いである。

▲川北はいまも完全試合のグローブを手にする
1977(昭和52)年はこうして暮れていった。王貞治選手の本塁打世界記録、北海道・有珠山の噴火があった年。世界的にはニューヨーク大停電、ハイジャックされたルフトハンザ航空機に特殊部隊が突入して解決した事件があった。この一カ月前に起きた日本航空機ダッカハイジャック事件との対比でよく覚えている。日本の弱腰さとドイツの強面さが比べられていた。
当時もいまも、天災、人災、事件、紛争は何かしら起き、スポーツ的には記録が塗り替えられていく。変わらないもの、変わるもの。繰り返されるもの、進化、成長するもの。改めて俯瞰すると味わいは尽きない。

▲前橋・東照宮での必勝祈願
敷島球場使い新年合宿
新年、駒形神社へのランニングしながらの祈願、前橋東照宮での年度祈願「かしこみ~」は例年通りだったが、すぐに球場練習の合宿入りとなった。
前橋の県営敷島球場横に「新花の茶屋」という割烹旅館があり、記憶が曖昧だが3泊4日程度だったと思う。
正直この話を聞いたときにはお腹が痛くなった。球場を使わせていただけるのはありがたいが、朝から晩まで練習となると気が重くなるのだった。
朝、6時ごろ起床。ジャージに着替えて散歩。日の出前、冬の群馬の早朝は恐ろしく寒い。キンキンとして顔が切れそうであった。霜柱を踏んで歩いた。
球場隣のオープントラック広場に着くとランニング、ダッシュ、体操、若干の筋トレ。宿に戻って朝食を食べる。
練習着に着替えて9時半~10時には球場入り。寒いので体を目一杯動かすようなことはなかったが、サーキットトレーニング、ダッシュの後にはキャッチボール、トスバッティング、ハーフバッティング、フリーバッティング、個人ノック、シートノック、ケースノックとフルメニューであった。
昼食に宿に戻って少し休憩。再び球場に向かうまでは和室で足を高くして横になっていた。冬場は日が落ちるのも早く、日が落ちると急激に冷え込んでくるので夕方で終了。これは助かった。

▲敷島球場を使っての練習。まずは入念に柔軟から
一番の目的は球場というものに慣れることであったのだろう。外野のフェンスからの連携、ファウルグラウンドでのカバーリングなど学校ではできない練習に時間をかけた。
さらにいえば、甲子園に出かけるとなると長い遠征になる。集団合宿生活に慣れておく練習でもあったと類推する。
この合宿で相澤雄司の歯ぎしりがすごいこともみなの共通認識となった。「ギッ!、ギッ!」と虫が鳴くような音。いびきは聞いたことがあったが歯ぎしり音は初体験だった。相澤よりは先に寝入ろうと思った。
挟殺プレーをマスターする
実はこの合宿で川北には大きな収穫があった。挟殺プレーを完全にマスターしたのである。
実は挟殺プレーは自信もなく、練習開始時にはまったくうまくできなかった。サードはスクイズをウエストしたケースなど試合の趨勢に決定的な影響を及ぼす挟殺プレーが発生する。何度練習しても三本間での挟殺がうまく行かなかった。
「ダメ、ダメ、ダメ。なんで。なーんでお前みたいに頭いいやつが出来ないのかなあ?」
あきれられて200%の皮肉を浴びた。
川北の頭の中には「ホームから遠い方に追っていく」「ボールは投げられるように右手で持って追う」「ランナーをよく見て、抱き着かれてインターフェアをとられないように」など既存の野球教科書のセオリーがバラバラに詰め込まれていた。
あまりにできないのでいったん休憩になり、そこでよくよく考えた。不器用なのでセオリーに優先順位を付けようと。何が一番大事か。「できるだけ早くランナーをアウトにする」と思い付いた瞬間に目の前が開けた。
そうか。どっちに追うかも、ボールをどっちの手で持っているかもそのこと自体は目的ではない。早く殺せばよいのだ。
ランナーを挟んだ瞬間からその両端にいる守備者は両端から全速力でランナーに向かう。守備者同士が全速力で向かってくるとランナーの方は止まるか、進むか、戻ってくるかしかない。正確に言うと戻ってくるには一度止まるので、止まるか進むかしかないのである。
であれば守備者同士が一定の距離に近づいた際に、双方ともに全速力で来たスピードを落とさずにボールを1度渡すことができれば間違いなくアウトにできる。ボールを持って追う守備者は右手にボールを持つが、反対から来る守備者はグローブタッチでよいのだ。
3本間はキャッチャーの高野昇と、23塁間はショートの堺晃彦、セカンドの田口淳彦と全速力で詰め合う感覚の調整は必要だったが、それからは百回百殺だった。
守備者間でのボールの受け渡しも1回で済みミスが減った。むしろ「早く殺す」は他のランナーの進塁阻止にも効果があり、ランナーを2人殺せることも出てきたのだった。
いまでもいろんな場面で挟殺プレーを観戦する機会がある。成功も失敗も見るが、その解説も含めて「できるだけ早くランナーをアウトにする」を見ること、聞くことは少ない。意外と認知されていない真理なのかもしれない。セオリーの優先順位をチームとしてどうしておくかの好例だろう。
競輪界の名伯楽に認められる
合宿中、OB諸氏も多く来られたが、鈴木保巳さんは特に印象に残っている。田中不二夫監督が夏の甲子園に出場された時の主将で、日大で野球を続けられたが競輪の世界に転じた。
競輪選手としても名をはせていたが競輪選手の育成者、名伯楽として有名な方だった。このとき、50歳前後だったろうか。体はがっしりと分厚く、ものすごいふくらはぎ、太ももだった。
鈴木さんはみなを車座に座らせると、「お前たちは何のために野球をやってるんだい?」と穏やかに、一人一人の目を見ながら問い掛けた。
「・・・・」
唐突かつ本質的な問いになかなか誰も答えられなかった。
「カワキタ、お前は?」
(誰も何も言わなけりゃ俺に来るわな…)と思いつつ、「目的とかではないですが、野球が好きなんです」と答えた。
「そうか、そうか。他には?」
「自分のためにやっています」
相澤が答えた。
鈴木さんのまなざしが、若干わが意を得たりと緩んだように見えた。
「そうだ。誰からもやれと言われたわけではない。自分で、自分のためにやってるんだ」
頭ごなしに押し付けるのではなく、一人一人が自分を自分でモチベートすることがいかに大事なのかを語られた。名伯楽と言われている人のまなざしを感じ、一人前の人と扱われて語り掛けられていることがうれしかった。

▲堺晃彦を指導する田中不二夫監督
かわきた・しげき

1960(昭和35)年、神奈川県生まれ。3歳の時に父親の転勤により群馬県前橋市へ転居する。群馬大附属中-前橋高―慶応大。1978(昭和53)年、前橋高野球部主将として第50回選抜高校野球大会に出場、完全試合を達成する。リクルートに入社、就業部門ごとMBOで独立、ザイマックスとなる。同社取締役。長男は人気お笑いコンビ「真空ジェシカ」の川北茂澄さん。
関連する特集・連載
-

2024.07.17
- 前橋新聞
【デジタルブック】 前橋新聞me bu ku 【特別号】 パワーモール前橋みなみ特集
-
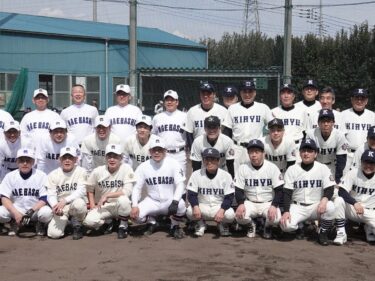
2023.06.29
- 見たい
【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶77】 終わりに
-

2023.06.26
- 見たい
【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶76】 エピローグ
-

2023.06.23
- 聞きたい
【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶75】 高校3年-7
-

2023.06.20
- 聞きたい
【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶74】 高校3年夏-6
-

2023.06.17
- 聞きたい
【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶73】 高校3年夏-5
-

2023.06.14
- 聞きたい
【昭和高校球児物語-前高 完全試合のキセキ-▶72】 高校3年夏―4



